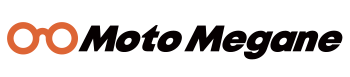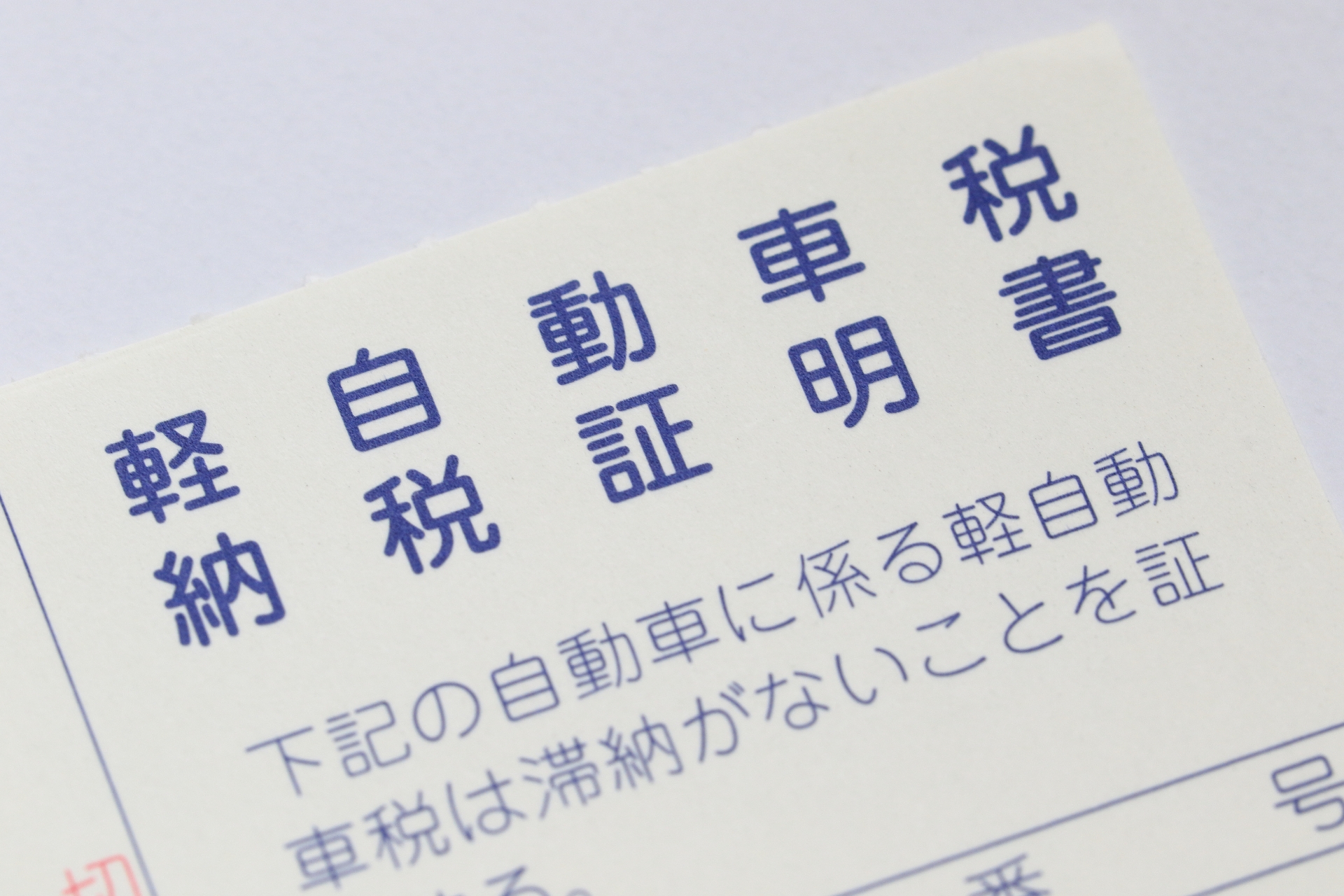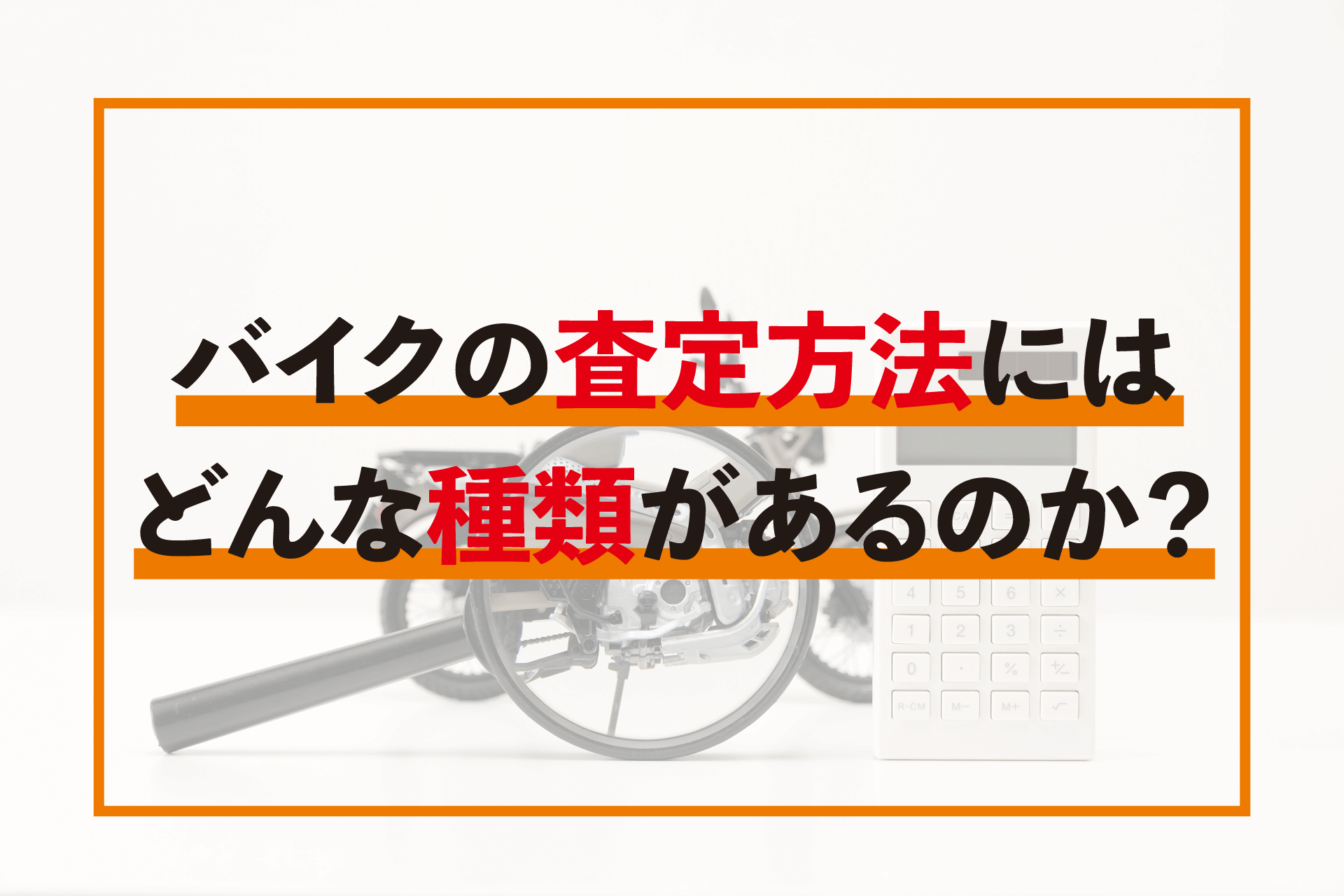住民票と車検証の住所が違う!これでも売却できるの?
バイクを売却しようとしたとき、車検証などに記載された住所と住民票の住所が異なっていることに気づくケースがあります。
特に、車検を受けた後に引っ越したときはこのような事態に直面することが多いのではないでしょうか。
では、バイクの車検証などの住所と住民票の住所が異なる状態でも、買取業者にバイクを引き渡せるのでしょうか。
売却時に住所はあまり重視されずトラブルになることは少ない
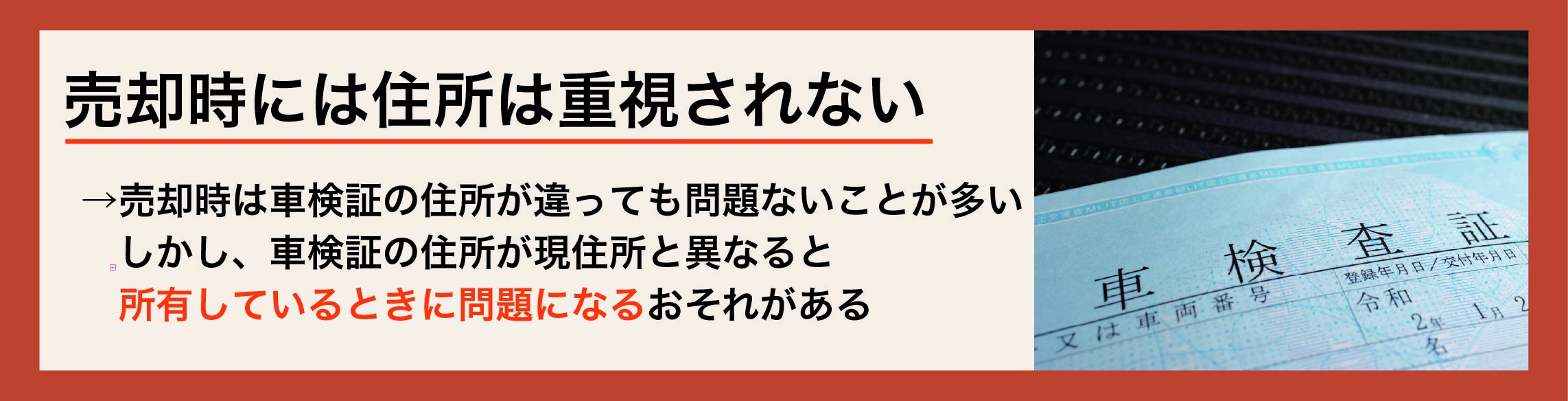
バイクを売却しようとしたとき、バイクの書類に記載されている住所と住民票に記載された現住所が異なっていることに気づくことがあります。
このような場合、バイクは売却できるのでしょうか。
バイクの売却では住所は問題にならない場合が多い
実は、車検証などに記載される住所と現住所が違っていても、買取手続きを受け付けてくれる業者は多いといえます。
なぜなら、バイクの売却では住所変更を確認するための住民票などの書類が必須ではないためです。
ただし、買取業者によっては住民票や戸籍謄本を求められる場合もあるため、不安に思った場合は事前に買取業者に確認するとよいかもしれません。
住所変更をしない場合、バイクを所有するときにトラブルを起こすことがある
上述の通り、バイクの住所変更を怠っても、バイクを売却するときには問題になりづらいといえます。
しかし、住所変更をしないと、バイクを所有している間にトラブルを引き起こすことがあります。
まず、売却にも関わる問題として、税金の納付書が旧住所に送付されてしまうため、税金を滞納、あるいは納付が遅れる可能性があります。
これは延滞金の発生につながるだけでなく、最悪の場合、財産の差し押さえにつながることもあります。
そして、税金の支払いにトラブルが起きると、バイクの売却に支障が出るおそれがあります。
特に、250cc以上のバイクを売却するときには、買取業者によって「自動車納税証明書」の提出を必要とすることもあります。
そのような場合、軽自動車税の滞納によって買取を拒否されるなどのトラブルにつながることが考えられます。
また、自賠責保険の手続きにも支障が出るおそれがあります。
保険会社に住所変更の届出をしていないと、万が一事故が発生した際に、保険金の支払いが認められない可能性があります。
このような場合、被害者への賠償責任を果たせなくなるという重大な問題につながりかねません。
加えて、警察や行政機関からの通知が旧住所に送付されてしまうため、重要な情報を受け取れなくなることも考えられます。
リコール情報や制度変更など、バイクの安全や維持にかかわる通知を見逃してしまうおそれもあります。
バイクの住所変更に必要な書類と手続きとは
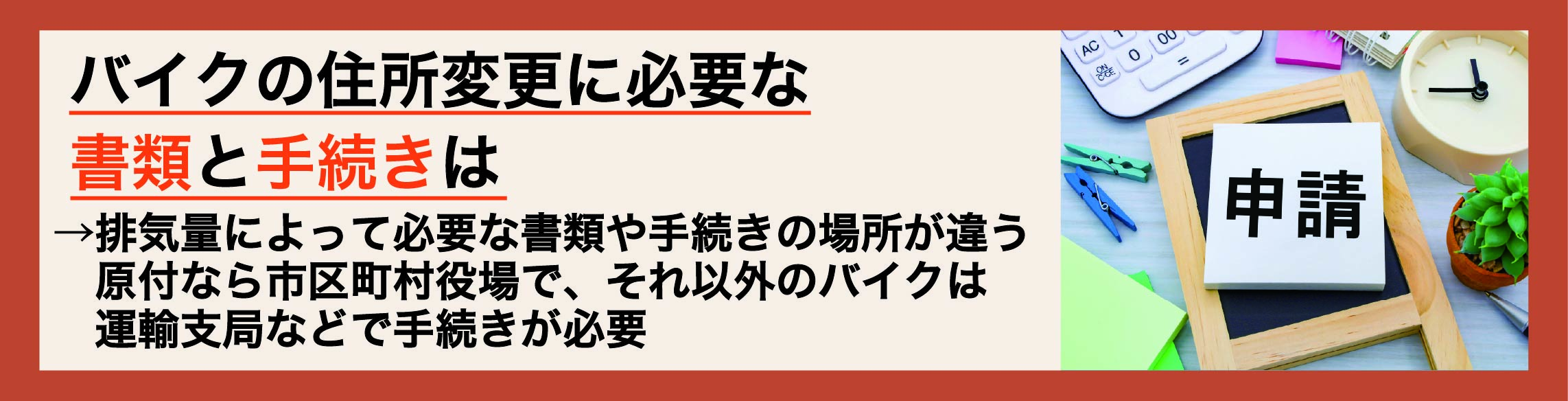
上述のように、バイクの住所変更は怠っても売却には支障がありませんが、バイクを所有する上でトラブルを生みかねません。
そのため、住所が変わったときは速やかにバイクの住所変更することが無難といえます。
では、バイクの住所変更にはどのような書類や手続きが必要なのでしょうか。
原付(50cc超125cc以下)の住所変更
排気量が50cc以上125cc以下の原付バイクの場合、住所変更は転居先の市区町村役所でおこないます。
同一市区町村内であれば廃車手続きは不要ですが、自治体が変わる場合には、旧住所の自治体で廃車手続きをおこなったうえで、新住所地で再登録する必要があります。
必要書類は廃車証明書、標識交付証明書、印鑑、新住所の住民票などです。
125cc超250cc未満のバイクの住所変更
排気量125cc超250cc未満の軽二輪に分類されるバイクについては、住所変更は国土交通省の運輸支局でおこないます。
このクラスのバイクでは軽自動車届出済証と自賠責保険証明書、印鑑、新住所の住民票が必要になります。
所轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要になります。
また、他人に手続きを依頼する際には委任状の用意も求められます。
250cc超のバイクの住所変更
排気量が251cc以上のバイクでは、同じく運輸支局での住所変更手続きが必要ですが、求められる書類がやや増えます。
自動車検査証、自賠責保険証明書、住民票、印鑑に加え、第一号様式のOCRシートや軽自動車申告書、手数料納付書などを陸運支局で入手し、その場で記入して提出する必要があります。
この手続きは、手数料がかかることに注意が必要です。
また、代理人がこの手続きをおこなう場合は軽二輪バイクの時の手続きと同じく、委任状が必要です。
まとめ
このように、バイクの住所変更を怠っていても、売却そのものができなくなるとは限りません。
しかし、税金や保険、通知などの面で不都合が生じるおそれがあり、トラブルを防ぐためにも車検証の住所が現住所になるように手続きすることが無難といえます。
売却の時までバイクをより安全に、トラブルなく維持するために、必要な時に必要に応じた手続きを行うことが求められます。